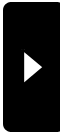2011年05月05日
日本は「無縁社会」なんかじゃない
誠に恐縮ですが、この場をお借りして今回の「東日本大震災」によってお亡くなりになられた方にお悔みを、未だ避難されている方にお見舞いを申し上げます。
(画像は、気仙沼市へ被災地支援に出掛けた、たっちゃん、みっきー、そして、冒険遊び場たごっこパークの常連っ子・ナオタカくんです。)
さて、去年は日本中で「しばらく会わない家族が、今どこにいるのか分からない」、「お爺さん、お婆さんは生きているのか、亡くなっているのか分らない」などと言う寂しい話ばかりでした。
そんな事が続いた為にメディアの人たちの中から、「日本は『無縁社会』になった」などと言うイヤな言葉も耳にしました。
でも、今回の震災に遭われた方たちを、外国のメディアの人たちの目から見た感想を聞くと。
その方たちは皆、「日本人は、この様な悲惨な目に遭っても冷静で沈着だ」とか、「人と人とが皆で助け合っている」また、「暴動や略奪(少しあったようですが)が殆ど無い」と、絶賛しています。
僕たち日本人の目から見ると、昭和の時代に比べて、今の平成の時代は確かに「お隣さんは何することやら」などと言う言葉も良く耳にするようになり、町のご近所さんのコミュニケーションも希薄になりました。
しかし、第三者でもある日本という国の外の人が見た印象を聞くと、日本は、日本人は、まだまだ捨てたものではないんだなと嬉しくなりました。
そして、たっちゃん、みっきーを中心とした「ゆめ・まち・ねっと」の市民活動、島田公園で開かれている「冒険遊び場たごっこパーク」はまさに、その様な人と人との絆、繋がりを求め、それらを育んでいく活動になっているのです。
Posted by しげちゃん・のりちゃん at
18:40
│Comments(0)
2011年05月03日
遊び場、たまり場が広がることを期待
「冒険遊び場たごっこパーク」には以前から、県内外の大学の学生さんが、ゼミの一環だったり、卒論の取材だったり、実習だったりと、大勢訪れてくれていました。
そして、今回お会いした方は、画像中央に映っている群馬県から来てくれたIさん。
僕はIさんに「何故ここに?、どうしてここを?」と、伺いました。
Iさんは、こうおっしゃってくれました。
「私は、この様な活動に大変関心があって、『卒業論文の題材』にしたくてインターネットでこの『たごっこパーク』を知って見学に来たんです」
僕は、この様な傾向を以前から見てきて改めて思いました。
たっちゃん、みっきー、その仲間の方たちの活動は間違いなく世の中に拡がっている。
そして、間違いなく理解され、認識され、必要とされていると。
そして更に、上に記した様に、これからの日本を担っていく若者たちがこの活動に関心を持ってくれるということは、将来は彼等、彼女等が生まれ育った故郷や、今生活している地域にも「たごっこ」のような子どもや大人の「遊び場、たまり場」を築く活動を拡げてくれるだろうと。
この事は、心から嬉しく、心から喜びたい限りです。
Posted by しげちゃん・のりちゃん at
12:07
│Comments(0)
2011年01月25日
焚き火を使った超ウマ裏技
例によって、相棒ののりちゃんと島田公園に行き、子どもたちの元気な顔と遊びっぷりを見に行って来ました。
いつも皆が集まる銀杏の木の下は、黄葉によるきれいな絨毯が敷き詰められていました。
冬の装いを見せる島田公園でしたが、寒い寒いと言っていたのは、オヤジの僕だけで、冒険遊び場の子どもたちは夏も冬も関係なく、いつもの笑顔を見せてくれ、いつもの歓声を聞かせてくれました。
ある子たちは、マシュマロを空中に飛ばし、他の子がそれを手を使わずに口でキャッチする遊びに興じていました。
見事な軽業です。
でも…バカバカしい(笑)
また、ある子はサッカーをやり、ある子はキャッチボールをやっていました。
それぞれの子どもが自由にやりたいことをして遊ぶ、いつもの「たごっこ」の光景でした。
そして僕は、あるお子さん連れのお母さんから焚き火を楽しめる冒険遊び場ならではの「超ウマ裏技」を教えてもらいました。
それは、マシュマロを木の串に差し、焚き火で数秒あぶって食べるというものです。
表面がほんのりキツネ色になったマシュマロの中は、何となんと、ショートケーキの上に乗っかっている生クリームのようになっているではないですか。
外は少しこんがり、中はとろ~り。
ある女の子は、マシュマロをあぶり過ぎて真っ黒にしちゃいました。
でも、さすが冒険遊び場たごっこパーク!
その子は真っ黒になったマシュマロを事も無げに美味しそうに食べました。
子どもにしてみれば、自分の手で作った物は、どうなろうと美味しい物なのかもしれません。
僕は思いました。
「このとろ~りを冷やせば、冷たいソフトクリームになるかなぁ」と。
喰い意地が人一倍張っている僕が、考えそうな事です。
でも、これは本当にイチオシの「超ウマ裏技」です。
是非、皆さんもお試しご覧あれ!!!
ちなみに、僕がこのお母さんとお会いしたのは、その日が初めて。
でも、アッと言う間に昔からの知り合いの様にオシャベリが始まってしまうのが、ここ「たごっこパーク」なのです。
冒険遊び場たごっこパークのブログ⇒こちら
Posted by しげちゃん・のりちゃん at
00:27
│Comments(2)
2010年11月12日
全国から注目の冒険遊び場たごっこパーク
下の記事に書いた男性Oさんとお喋りをしていたら、「宇治に冒険遊び場つくろう会」の代表・Sさんと言う女性も加わり、色々とお話を伺う事が出来ました。
Sさんに、この様な活動を始めたキッカケは、何だったんですかと伺うと、
「私が学生の時に、身近でこの様な活動を見て、こういう『子どもの遊び場』が宇治にも絶対必要、絶対作りたいという気持ちが湧いてきたからなんです」と熱く、熱く語ってくれました。
「私たちの活動は、始めてからまだ2年ほどで『遊び場』を開催できるのも1年に4~5回なんです。でも、8月に『遊び場』を開催したら3日間で大人が33人、子どもが55人も来てくれたんですよ」とのこと。
この日も宇治から2歳の子から中学生までが11人、大人が14人も来てくれていました。
たっちゃんが言っていました。
「しげちゃん、僕たちがこの活動を始めた頃はね、全国でこういう活動をしている人を招いてね、色々と教えてもらっていたんだよ。
でもね、最近はこうして逆に遠いところから『たごっごパーク』を見学して、参考にしてくれる人が数多く来てくれるようになったんだ」と。
ゆめ・まち・ねっとの活動には、疑問、反論を投げかける人もいるでしょう。
しかし、現実は、今このような活動が全国で急速に拡がっているのです。
ということは、多くの大人、多くの子どもがこうした遊び場、居場所を必要としている証拠です。
今回のたごっこパーク訪問で、僕とのりちゃんは、またまた改めてこの様な活動の大切さ、必要性を教えてもらったのです。
Posted by しげちゃん・のりちゃん at
08:21
│Comments(0)
2010年11月11日
人と人とが集うまちづくり
秋だというのに、島田公園「冒険遊び場たごっこパーク」の子どもたちは、いつもの小潤井川にダイブをしていました。
これぞ、たごっこ!
この日は、いつもの2倍、3倍の人で大賑わい。
僕は、たっちゃんに「これは一体なんぞや?」と聞くと、
「しげちゃん今日はね、京都の宇治市から『宇治に冒険遊び場つくろう会』の人たちが視察、見学を兼ねて遊びに来てくれたんだよ」とのこと。
すごい!京都から。
僕とのりちゃんが公園の中で秋の木漏れ日を浴びぬくもっていたら、宇治からいらした男性の方と一瞬目が合ったのです。
すると、その方が椅子を持って僕たちの横に来て、話し掛けてきてくれました。
初対面にもかかわらず、こうした子どもたちの遊び場を心地よいと感じる者同士、他人とも思えず、自然のうちに世間話に花が咲いてしまいました。
そのゆったりとした時間の心地よさ。
これこそが『冒険遊び場たごっこパークの良さ』であり、たっちゃん、みっきーやお仲間たちが目指す『人と人とが集うまちづくり』の原点だと感じました。
Posted by しげちゃん・のりちゃん at
10:54
│Comments(0)
2010年11月08日
子どもと遊ばない代表、副代表
先日、秋の気持ちよいお天気の日に冒険遊び場たごっこパークを訪問しました。
この写真は、みっきーが撮影してくれたものですが、冒険遊び場たごっこパークのスタッフたちの立ち位置がとてもよく表れている一枚だと思います。
僕とのりちゃんのインタビューに答えてくれているのが代表のたっちゃん。
布のリュックを背負って緑色のシャツを着ているのが副代表のおばっぴー。
おばっぴーは、東京と神奈川からやって来た方とおしゃべりしています。
臙脂色のシャツを着ているのがもう一人の副代表のまーくん。
まーくんは、ベルギーからやってきた青年・マノエルとおしゃべりをしています。
子どもたちがたくさん集う場を主催していながら、代表、副代表がこんな風に子どもと関わらずに過ごしている場というのはあまりお目に掛かれないのではないでしょうか。
子どもたちが遊ぶための場の提供だけをし、あとは子どもたちの様子をニコニコと眺めながら、来客の対応をする。
だからこそ、逆に冒険遊び場たごっこパークの子どもたちは自由に生き生きと遊ぶことができるのだと思います。
以前、たっちゃんが言っていた「冒険遊び場に必要なのは、子どもと遊ぶのが好きな大人ではなく、子どもが遊ぶのが好きな大人なんだよ」という言葉が思い起こされます。
さて、そんな大人たちに見守られて、この日も子どもたちは思い、思いに遊んでいました。
でも、子どもたちは思い、思いにと言っても、自分勝手に、ということとは大きく違うことが観察できます。
誰かが川から上がろうとすると、さっと手を差し伸べて、それを助けています。
のこぎりで苦労している小さな子がいると、お手伝いをしている年上の子どもがいます。
役割分担をして、ドラム缶風呂を沸かしています。
たっちゃんにその点を聞いてみました。
「そうなんだよねぇ、しげちゃん。冒険遊び場たごっこークで子どもたちの遊びを見ていると、子どもたちは、ただただ、自分が楽しむだけに遊んでいるわけではないことに気付くんですよ。
しかも、しげちゃんが観察した場面は、ご覧のとおり、僕も他のスタッフもこんな風に過ごしている中での姿だから、先生や指導者に言われたからやっているわけではないということもわかりますよね。
子どもたちの心の中から自然と出てくるやさしさ、思いやり、 助け合い。それは大人から知識・技能を教えてもらう塾とか習い事じゃなくて、子どもたち同士で交わる遊びの中でこそ、育まれるんじゃないかと思うんだよね。
足繁く遊びに来るいわゆる「常連」の子どもたちほど、そうした姿を見せてくれるから、遊びの大切さを本当に教えられますよ。」
なるほど、遊びの中で獲得した社会性や協調性は、きっと、子どもたちの一生の宝物なんでしょうね。
そんなことを思っていたら、みっきーがひと言、付け加え。
「でもね、しげちゃん。それはあくまでも結果であって、私たちスタッフが『よーし、子どもたちに社会性や協調性を身に付けさせるぞー』なんて思ったら、結局、塾や習い事と同じになっちゃうと思うんですよ。」
なるほど、なるほど。
私たち大人は、効率優先、結果優先の社会の中で忘れられてしまっている子どもたちの遊びの価値を、今一度、考えてみる必要がありそうですね。
Posted by しげちゃん・のりちゃん at
18:23
│Comments(0)
2010年10月25日
遊びの時間
もう、とっくのとんまに夏休みも終わりました。
野山や川や海、公園から響いてきた子どもたちの元気な声も、セミの声と共に聞えなくなってきた今日この頃です。
と言いたいところですが、夏休み中も子どもたちの元気な声を街中で聞くことはありませんでした。
たっちゃんが「新聞にこんな記事が掲載されていたよ」と教えてくれました。
7月5日付けの静岡新聞に掲載された民間調査結果。
夏休みに小学5~6年生が過ごした時間。
・テレビ、DVD 2時間17分
・ゲーム機 1時間22分
・家でごろごろ 1時間07分
・自宅で勉強 1時間02分
また、全体の30%は夏休みでも塾通いで、塾での勉強は2~3時間。
そして、これらに対して、
・外での遊び 1時間36分
これもたっちゃんから教えてもらった話。
高名な児童精神科医・佐々木正美先生が遊びの意義について、 こんなことをおっしゃっていますよと。
「昔は十分な自然がありましたから、だれも自然の大切さを語る必要がありませんでした。
近年になって自然が不足してくると、その大切さがクローズアップされてきましたね。
それと同様に、子どもにとっての遊びは当たり前のことでした。
今、生活環境の変化で上手に遊べない子が増えてきて、ちょうど子どもにとっての遊びの意義が、水や空気のように大切な意味をもってきた、と思います」
なるほど、僕やたっちゃんが幼かった頃は、DVDもテレビゲームも無く、佐々木先生がおっしゃるような自然の中で、自然を相手に仲間とともに遊ぶのが普通の遊びでした。
しかし、今の子どもたちを取り巻く環境はどうでしょうか。僕たちが幼いころ普通だった事が普通ではなくなっていませんか?
静岡新聞に掲載されていたデータを、皆さんはどんなお気持ちでご覧になられたでしょうか…。
先日、秋晴れの冒険遊び場たごっこパークをのりちゃんと二人で訪れました。
秋だというのにまだ川遊びをしている子どもたち。
ドラム缶風呂を楽しむ子どもたち。
ここにはまだ、『遊びの時間』がゆったりと流れていました。
Posted by しげちゃん・のりちゃん at
09:32
│Comments(0)
2010年09月23日
人の温もりとたっちゃんの思い
今回は、たっちゃんが今までに、僕に送ってくれた便りの中にしたためられた「たっちゃんの、今の夢と想い」を、皆さんにお伝えしたいと思います。
それはこんなお便りでした。
もう、かれこれ35年も前のこと。原因は覚えていませんが、父親に叱られて、「お父さんのバカっ!」と反抗をしたら、「親にバカなんて言う子は出てけっ!」と家の外に放り出されました。
もうすっかり、辺りは暗くなっていた時間に、とぼとぼととりあえず、駅へ向かいました。
駅へ着くと、ちょうど列車から隣の家のおばちゃんが降りてきました。
「あれ、たっちゃん、こんな時間にどうしたの?」
かくかくしかじかで、家を出されたということを説明しているうちに涙がこぼれてきました。
「おばちゃんが一緒に謝ってあげるから、おうちへ帰ろう。」
おばちゃんが取り成してくれて、家にあげてもらいました。
映画「ALL WAYS三丁目の夕日」などを観てもそうですが、きっと、かつては地域の中にこんな姿が日常的にあったことでしょう。
僕のことを小さいころから知ってくれているおばちゃんがいて、だから、そのおばちゃんがこんな風に関わってくれる。
いつしか、そういう日常がこの国では失われていったように思います。
NPO法人ゆめ・まち・ねっとの活動の柱「冒険遊び場たごっこパークは、そんな時代にあって、子どもたちに居場所を提供しようとする活動です。
いつの日か、こうした活動がいらなくなる社会が築かれんことを願いながら取り組んでいます。
以上です。
僕は思いました。たっちゃんは、幼い頃「人と人の繋がり」、「温かい人の温もり」、「思いやりのある人が集まる街」この様な体験を何度も、何度も積み重ねた想い出があるから、今のたっちゃんの強い志があるんだなと。
更にこんなことも思いました。
たっちゃんのこの様な体験は、たっちゃんのみならず多くの日本人が幼い頃に体験していると思います。
しかし、今の冷えた社会の中でこの様な「人の温もり」、「温かい町」を人は、いつの日か、どこかに置き忘れて来ているのではないのではないでしょうか・・・・・。
Posted by しげちゃん・のりちゃん at
00:54
│Comments(0)
2010年08月14日
活動を続ける覚悟
第一部の新朗読が終わり、第二部のたっちゃんと直さんとの「トーク」が始まりました。
僕は、お二人が語る「これからのまちづくり、子どもたちの遊び場、居場所づくり」と、これからの子どもたちに何を、どうやって与えていくのかと言う熱い、熱いお話に共感しきりで、「ウン、ウン」と、首を振り続け、首と肩がコリコリになってしまいました。
「トーク」が終わると、直さんがが会場にいらしていた方に、「何かご質問がある方、いらっしゃいますか」と促しました。
数人の方から質問があり、最後の方からこの様な質問がありました。
「子どもたちを自由に遊ばせ、もし事故が起き怪我をしたらどうしますか」。
実は、僕もたっちゃんに始めて出会った4年ほど前に、活動の内容を聞いた際に全く同じ質問をしたのです。
たっちゃんは先ず、意外なことを言いました。
「子どもたちが遊ぶ中で起こるケガを防ぐ一番良い方法はこんな活動をやらないことです。」
それから、たっちゃんは言葉を選びながら、静かに、そして強く、話を続けました。
「社会の中から子どもたちが自由に遊べる環境が失われました。替わりにこんな子どもになれ、あんな子どもになれと大人が期待される子ども像がたくさん生まれました。その子ども像に近付くためにはこんなことを学びなさい、あんなことを習いなさいというシステムが揃いました。」
「大人が理想とする子ども像に近付けない子どもは落ちこぼれと言われるようになりました。結果、小中学生の不登校12万人、高校生の不登校・中退14万人という結果を招きました。その先、引きこもり、ニートと呼ばれるような人たちは何百万人とも言われています。これが先進国と呼ばれる日本の姿です。」
「私たちの活動はこの富士市の中のほんの一地域の子どもたちを対象にした小さな活動に過ぎません。こうした数字をたったの一人も減らすことができないかも知れません。だけど、何かをしなければ、たったの一人も救えないと思います。」
「活動の中で子どもたちの怪我が起こったとき、それをきっかけに活動が中止になるのか、継続できるのか。それは、子どもたちと自分たちとの間にどれだけの信頼関係を築けるかということに懸かっていると思います。怪我をした子どもが自分が冒険をしてみたくて、やってみた結果がこうなったと納得するか、スタッフの責任だと思うか。」
「この活動は、我々大人がどれだけ、子どものことを信じることができるのか、ということが問われている活動だと思っています。」
たっちゃんとみっきー、そして、お手伝いしているスタッフの方たちの活動は、多分始めた頃は、地域の方にも、なかなか受け入れられなかった事も多々あったと思います。
しかし、現在ではこの活動が市内、県内どころか全国からも注目をされる活動になったのが現実です。
ということは、多くのお父さん、お母さん、大人が、今の社会と子どもと大人にとって、この様な場所と、活動が必要不可欠だと気付き出してくれた証拠ではないのでしょうか。
それは、たっちゃん、みっきー、スタッフの方たちの、子どもたちに遊び場を与え、居場所を与え、今の冷えた街を温かな街に変えたいという、熱く、強い志が成し得た物だと思います。
子どもの遊びには、リスクの無い遊びなどありません。
子どもの遊びには、リスクがあるから、子どもは夢中になるのです。
子どもの遊びには、リスクがあるから、得難いものを得ることが出来るのです。
冒険遊び場たごっこパークと同じような主旨で活動する団体が8月29日(日)、全国117箇所で同時に冒険遊び場活動をするそうです。
詳しくは⇒こちら
冒険遊び場たごっこパークもいつもの定例開催日ではありませんが、臨時開催されます。
Posted by しげちゃん・のりちゃん at
08:00
│Comments(0)
2010年08月13日
新朗読×杉山直
6月19日(土)、富士市フィランセに於いて「男女共同参画週間」記念事業の冒頭で「ゆめ・まち・ねっと」主催により、杉山直さんと、そのスタッフの方たちが新朗読『ヤクーバとライオン』、『びゅんびゅんごまが、まわったら』を会場に来ている来場者の方たちに披露してくれました。
この新朗読を拝見し、いつも思う事は、プロの方たちによる音響、照明、映像、そして朗読によって「目、耳、体」で感じる『本物』の感動を頂ける喜びです。
そして、それは理屈など無く、老若男女誰もが共通した感動なのです。
新朗読×杉山直を鑑賞できる次の機会は9月4日(土)富士市交流プラザで開催される『星の王子さま』です。
0歳から入場OKなんだそうです。
詳しくは⇒こちら
Posted by しげちゃん・のりちゃん at
18:43
│Comments(0)